金融に未来はあるか:ジョン・ケイ著/ダイヤモンド社 書籍レビュー
2017年09月05日
著者のジョン・ケイ教授は、投資銀行は金融取引や商品化のブラック・ボックス化、巧妙なリスクの転嫁などで自己の利益を図るようになったことを批判する。金融の使命は仲介業として預金などの個人の資金を実経済の需要につなぐこととし、その原点に戻るように提言する。
ジョン・ケイ著「金融に未来はあるか」(ダイヤモンド社)の原題はOther People's Money で本書の282ページにある「投資銀行は……よそ様のお金を使って上級職員のためにトレーディングをするようになってしまった」でその意味が分かる。
この場合の投資銀行はJPモルガンなどの金融コングロメリットも含んでいる。金融イノベーションの名のもとに証券化、デリバティブなどの金融ビジネスが進展したが、金融取引や商品化のブラック・ボックス化、巧妙なリスクの転嫁などで投資銀行自身がレバレッジも悪用し、トレーディングで自己の利益を図るようになったことを批判している。
リーマン危機に至るまでの金融規制当局の無見識について、著者は2006年のバーナンキの「あらゆる規模の金融機関が過去20年間、リスクの測定、管理能力において大いなる前進を遂げました」との発言を引用し鋭く批判する。金融の使命は仲介業であり、預金などの個人の資金を実経済の需要につなぐこととし、その原点に戻るように提言する。英国のスチュワードシップ・コードのバックボーンにあるケイ・レポートの責任者らしく、資産運用会社とスチュワードシップの重要性についても強調する。
(文責:門多 丈)
>>書籍の詳細 [Amazon.co.jp]
この場合の投資銀行はJPモルガンなどの金融コングロメリットも含んでいる。金融イノベーションの名のもとに証券化、デリバティブなどの金融ビジネスが進展したが、金融取引や商品化のブラック・ボックス化、巧妙なリスクの転嫁などで投資銀行自身がレバレッジも悪用し、トレーディングで自己の利益を図るようになったことを批判している。
リーマン危機に至るまでの金融規制当局の無見識について、著者は2006年のバーナンキの「あらゆる規模の金融機関が過去20年間、リスクの測定、管理能力において大いなる前進を遂げました」との発言を引用し鋭く批判する。金融の使命は仲介業であり、預金などの個人の資金を実経済の需要につなぐこととし、その原点に戻るように提言する。英国のスチュワードシップ・コードのバックボーンにあるケイ・レポートの責任者らしく、資産運用会社とスチュワードシップの重要性についても強調する。
(文責:門多 丈)
>>書籍の詳細 [Amazon.co.jp]
- at 12時57分
- | コメント(0)
- | トラックバック(1)
この記事に対するご意見・ご感想をお寄せください。
この記事に対するトラックバック一覧
こちらのURLをコピーして下さい

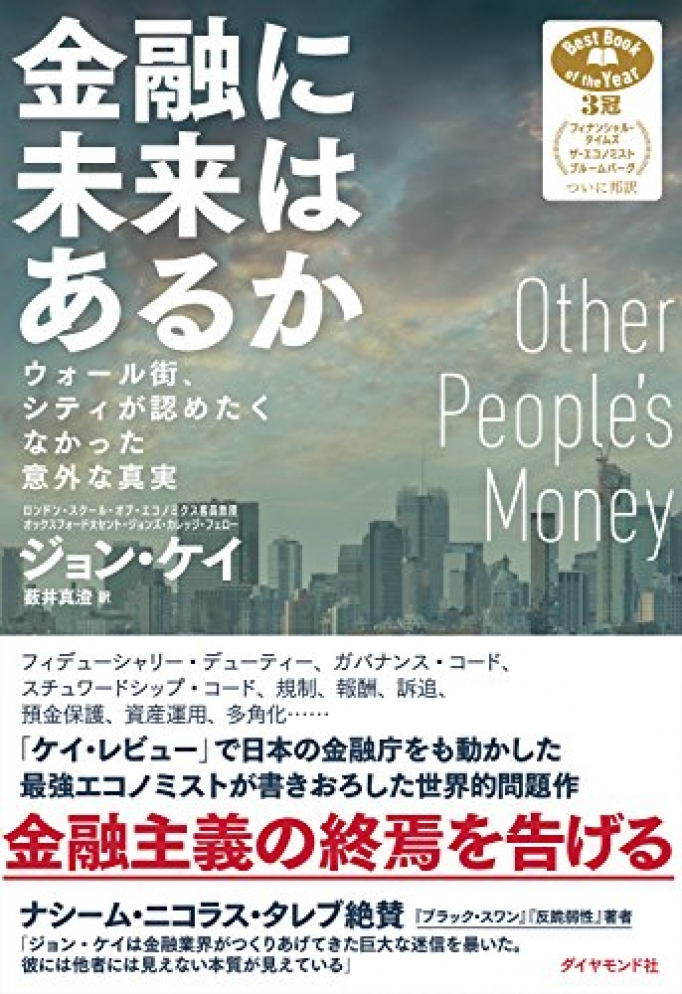

サイト名: - 2019年6月26日 12時53分
タイトル:
内容:
URL:/blog/blog_diaries/blog/blog_diaries/receive/265/