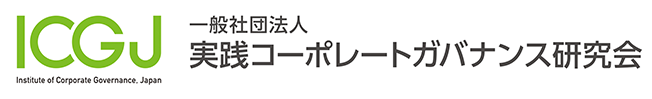2024年 月例勉強会
2024/04/02
今後の勉強会スケジュール
【第151回】2024年4月17日(水)13:00~14:30
■ 題目:なぜ不祥事防止対策が失敗するのか ~数値偽装事件を防止するための提言~
■ 講師:樋口 晴彦 氏(警察庁人事総合研究官兼警察大学校付/危機管理システム研究学会理事)
【第152回】2024年5月21日(水)13:00~14:30
■ 題目:変わりゆく資本主義社会と上場企業のあり方を考察する ~持続可能な社会の構築のために我々は何をすべきなのか?~
■ 講師:
清水 大吾 氏(みずほ証券株式会社 グローバル投資銀行部門 サステナビリティ推進部
サステナビリティ・エバンジェリスト)
>> 過去の勉強会活動実績の一覧は、下記リンクよりご覧いただけます。
2024/03/12
【第150回月例勉強会】資本市場を意識したM&Aの意思決定 ~コーポレートガバナンス時代のM&Aとは?~
■講師:岡 俊子 氏(株式会社岡&カンパニー 代表取締役社長)
■講演内容:
2023年における日本企業が関わったM&Aは、金額ベースで17兆9千億円、件数ベースでは4015件であった。これは、金額ベースでは22年から5割増えているものの、件数ベースで見ると過去最高となった22年からは7%の減少となっている(レコフデータ調べ)。特徴的なディールは、日本産業パートナーズ(JIP)による東芝の非公開化、円安のなかでも日本製鉄によるUSスチール買収などの海外大型ディール、大正製薬やアウトソーシング、ベネッセなどのMBOが相次いだことなどが挙げられる。大きなトレンドとしては、M&Aは年々増加している。そのM&Aに対して資本市場は、企業価値を上げるディールを期待するが、実態は、そうなっていないケースが少なくない。何が原因なのだろうか?また最近では、資本市場を出て行く動きが目に付く。前述のMBOや東芝の件がその事例である。こういった動きが起こる背景には何があるのだろうか?コーポレートガバナンス改革が浸透した現在、企業価値向上を目的とした成長戦略や事業ポートフォリオの見直しのため、資本市場を意識しなければと自覚する企業が増えている。そこで今回のセミナーでは、取締役会において、今後ますます重要な議題となるこのテーマを取り上げることとなった。長年にわたりM&Aの最前線で活躍されている講師をお迎えし、企業がM&Aへの向き合い方をどう変えて来ているのか、これからの課題は何かについて解説していただいた。
■ 講師略歴:
1986年に等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(アビームコンサルティングおよびデロイトトーマツコンサルティングの前身)に入社。その後グループ内移籍等を経て、株式会社岡&カンパニーでは、M&A戦略や経営戦略の策定支援、M&Aのディール支援、ポストM&A(PMI)のコンサルティングサービスを提供。明治大学MBA(グローバル・ビジネス研究科)専任教授。ソニーグループ株式会社社外取締役、株式会社ハピネット社外取締役、日立建機株式会社社外取締役、ENEOSホールディングス株式会社社外取締役、株式会社産業革新投資機構(JIC)社外取締役。著書は、「資本コスト」入門、「子会社売却」の意思決定(いずれも中央経済社)など。一橋大学卒業、米国ペンシルベニア大学ウォートン校MBA。
2024/01/15
【第149回月例勉強会】コーポレートガバナンスの実質化:現状と未来
■講師:松田 千恵子 氏(東京都立大学 大学院 経営学研究科 教授/
経済経営学部 教授)
■講演内容:
2015年に公表されたコーポレートガバナンス・コードは主として監督の強化を謳い、高い遵守率を見せたが、形式的な対応との批判もまた強かった。こうした流れに対し、2023年にはその当初より、コーポレートガバナンスの実質化が強く打ち出され、企業経営は資本コストを認識した効率的な経営や適切な事業ポートフォリオ管理で企業価値の向上を目指すべき段階に来ている。また、取締役会にはモニタリングの機能を果たすための取締役会のダイバーシティやスキルマップによる実効性の証明が課題となり、投資家の信認を得るための開示や対話の重要性が、企業経営・取締役会双方に求められている。そこで今回は、企業戦略とコーポレートガバナンス研究の第一人者である松田千恵子先生をお招きし、「コーポレートガバナンスの実質化」の現状と、企業経営の未来についての実証研究も踏まえお話しいただくことになった。
■ 講師略歴:
株式会社日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業等を担当後、ムーディーズジャパン株式会社格付けアナリストを経て、株式会社コーポレイトディレクション、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社でパートナーを務める。企業経営と資本市場にかかわる研究、教育及び実務に注力する。事業会社の社外取締役、公的機関の委員等を務める。東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士、筑波大学大学院企業科学専攻博士課程修了。博士(経営学)。